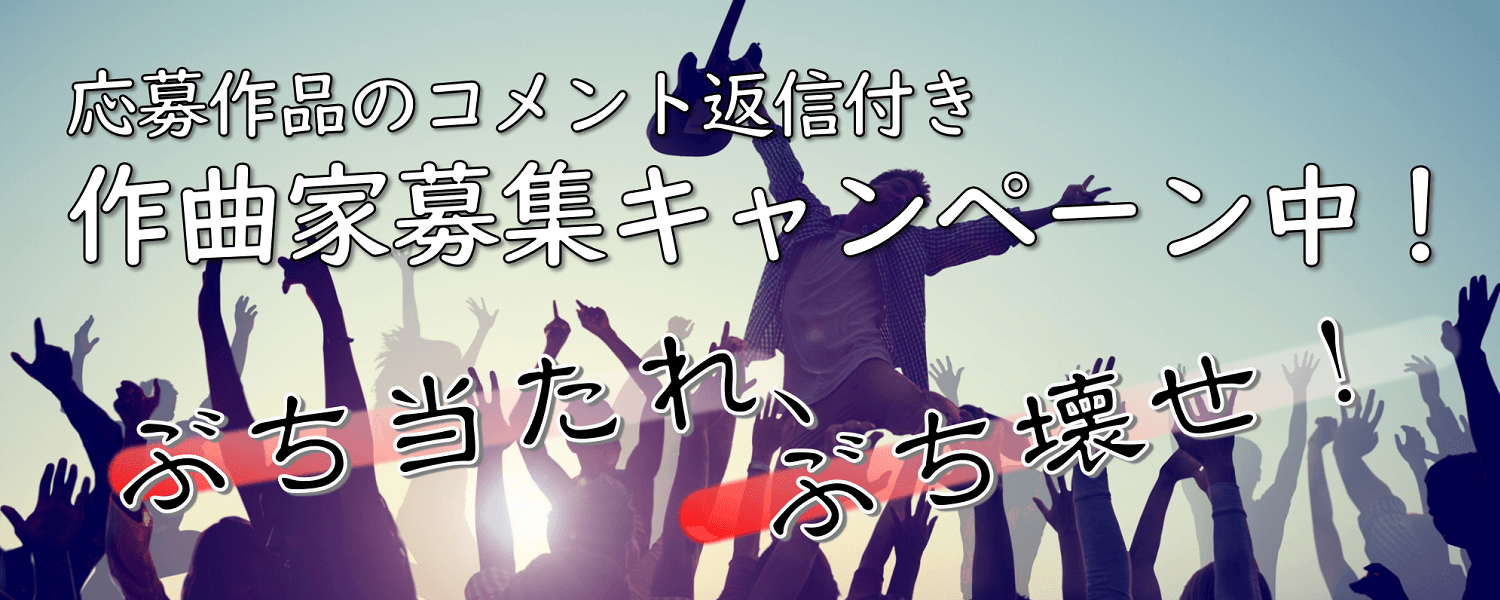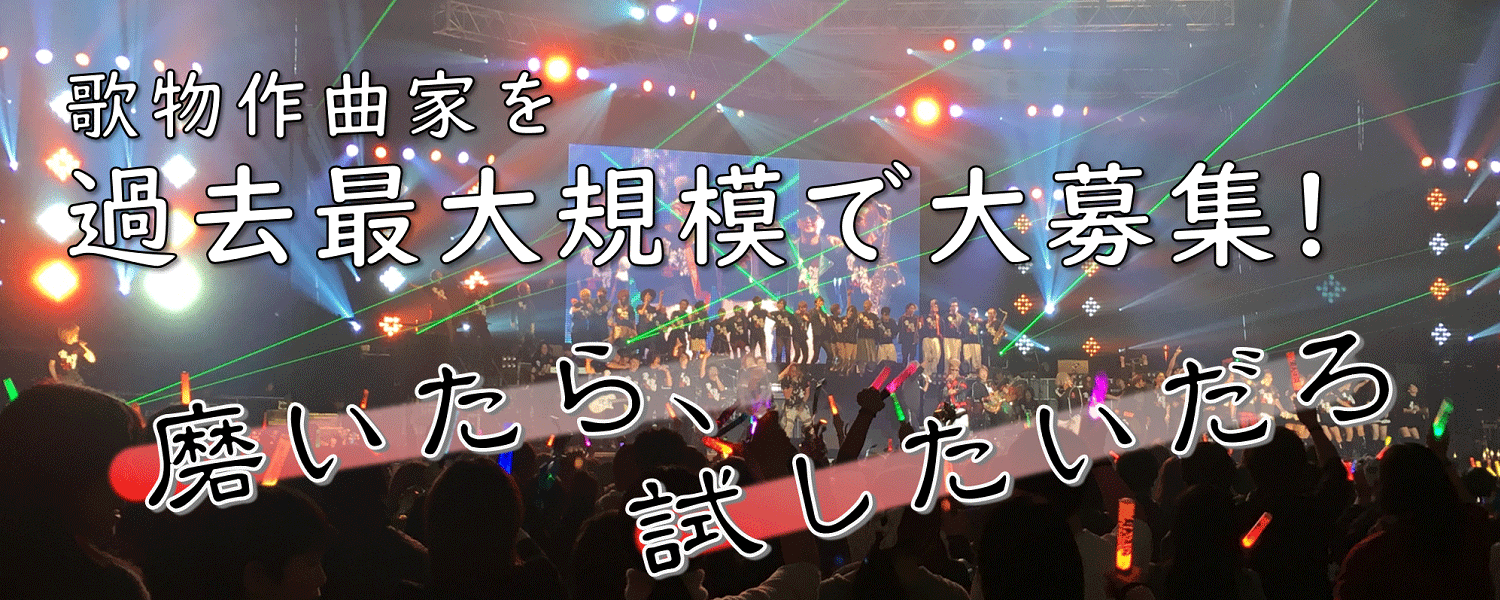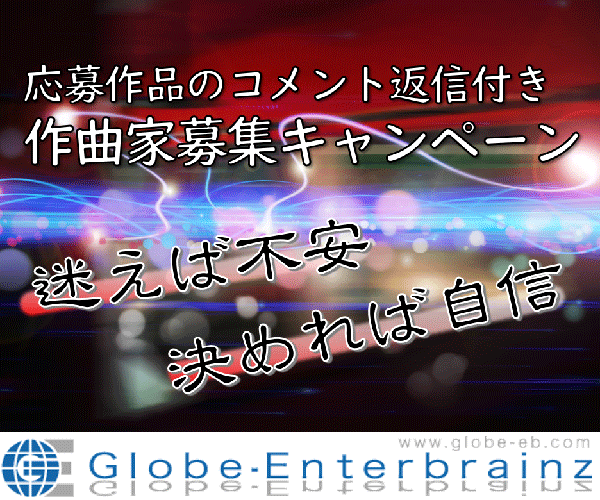昨年やらせていただいた長期間に渡るゲームのプロジェクトですが、様々な学びや気付きがありました。
そんな中、制作の中で最も記憶に残ったのは何か?と考えると、やはり大型の弦楽器と管楽器を生で録音させてもらえたことです。
それまでは、バイオリンやギターなどの単独楽器を生演奏に差し替えることはあったのですが、もっと大きな編成でまるっと生演奏を取るのは自分にとっては初めての経験だったので、レコーディングの日まで「果たしてうまくいくだろうか?」「どんな音で録れるだろうか?」とワクワクとドキドキが入り交じる心理状態で過ごしていました。
さて、レコーディング日が決まると、生録音に向けての準備をしなければなりません。
今回は、弦楽器が10型(10−8−6−6−4)、金管がTP3、Hr4、Trb2、B.Trb1、Tuba1という基本編成をもとに、曲によってホルンが増えたり木管のソロが足されたり、というとてもリッチな条件でレコーディングさせていただきました。
基本的には、録音対象曲のモックアップ(=打ち込み)のデータのMIDI出し→それを譜面制作ソフトで譜面化→録音用のカラオケステムとテンポトラックの用意、という順番でRecの仕込みをしていくのですが、ある曲でストリングスが「速いテンポで跳躍のある16分音符の連続」というのが何小節にも渡って続く・・・という、「これは生演奏は無理かな?」というフレーズが出てきました。ただここのフレーズは、曲のキモになる部分でどうしても生演奏を取りたかったので、フレーズをDivisi(=分割)にした譜面を持っていくことにしました。音大生の頃に、自信満々で持っていった譜面を学生オケにやらせたら、全然上手に弾いてくれなくメタメタになってしまい「ああ、こんな演奏不可な譜面を書いてしまった自分が悪いんだ・・・」と思ったトラウマが蘇ったからです。
そしてストリングス録り当日。リーダーの1stバイオリンの方に、当該譜面を見せて「ここのフレーズが難しいと思ったのでDivisiにしたんですけど…」とお伝えすると「全然Divisiにしなくても大丈夫ですよ、弾けますよ」とまさかの即答。しかもDivisiしていない譜面を用意して無いことをお伝えすると、「このDivisiになってる2段を合わせた状態で演奏すればいいんですよね?大丈夫ですよ!」とまた即答。
難しい譜面を書いていた気でいたのでその返答に呆気にとられていたのですが、チューニング、サウンドチェック後に録音が始まった瞬間に自分の心配は杞憂だったことを思い知らされました。
とにかく、1テイク目から自分の心配はなんだったんだ!というような素晴らしい演奏で、「あれ、こんな曲書いたっけ?」と思うような、自分が書いた楽曲に命が吹き込まれたような感覚になり、感動と鳥肌でその後のディレクションするのが難しいくらいでした(笑)。演奏がうまい、と一口に言うとそれまでなのですが、当日初めて聴く曲なのに譜面が求めている内容を一瞬で理解する能力、つまり嗅覚の鋭さが本当に素晴らしく、こちらが多くを説明せずとも最初から意図の通りに演奏してくれる点にプロのミュージシャンの凄さを再認識しました。
現在はソフトシンセの進化により、あまり生演奏で録らずともそこそこ良い音が作れるのですが、やはり弦を擦る感じやユニゾンを作った時の微妙に空気が揺らぐ感じ、またリリースの歯切れの良さやアタックの立ち上がりの良さなどは、現在の技術を持ってしても生でしか味わえないものですし、何より打ち込みと違い楽曲が「生きてる感じ」になるので、楽曲を一生懸命書いてよかったなぁと報われる瞬間を味わうことが出来ました。
また今回のレコーディングの経験で、自分が必要以上に演奏難易度に配慮しすぎていたんだなと気づくこともでき、それ以降のアレンジもより自由に、より複雑にすることをためらわなくなったので、編曲の引き出しが広がったことも大きな収穫のひとつでした。
インスト制作は自宅でソフトシンセのモックアップのみで完結することもままあるのですが、「自分の演奏(発想)」のみで楽曲を完成させるので、自分の発想以上の表現をなかなか思いつかない状況であるとも言えると思います。しかし、生演奏という別の人の発想がそこに加わることによって、音楽表現の幅がグッと広がる化学反応をまざまざと見ることが出来たのは、自分にとって一つのターニングポイントになったと思いました。
さて、プロのミュージシャンの凄さに感動しっぱなしのストリングスレコーディングでしたが、長くなったのでこの辺りで終わりです。
次回は、そんな中でももっとこうすれば良かった!と思った反省点などについて書ければと思っております。